松之山で暮らし続けるための人と知恵が集まる場

佐藤美保子です。生まれは奈良市です。親の仕事の都合で、浦和、名古屋、宇都宮、大学で仙台。県庁所在地で暮らしてきたんです。
20代後半になってから東京で暮らしたいと思い立ってハローワークに行ったら、田んぼ研修があるごはん屋さんがあった。田舎が好きだけど、田舎暮らしや農業の体験がなかったから、仕事しながら体験できるっていいじゃんって働くことになりました。そのごはん屋さんが社員研修用に借りていたのが、松之山の田んぼなんです。

<十日町市初の協力隊に>
2009年に嫁に来て、丸10年がすぎました。旦那さんは、わたしたちが田んぼ研修に来たときは個人として町の貸し農園に関わってました。
5月に結婚して、しばらく仕事しないよって言ってうちにいたんですよ、わたし。そしたら、9月に十日町市が初めて地域おこし協力隊の採用を始めることになって、地域の方から「交流が縁で東京からお嫁にきたし」って声をかけていただいてね。翌年2月に出産予定だったんですけど、もともと健康だったのと、嫁ぎ先の家族の協力や働き方のフレキシブルさもあったから、産前1ヶ月、産後1ヶ月の産休を取りながら地域の人と関わるお仕事を楽しませてもらいました。任期中に子どもを2人産んで、後任が決まったタイミングで退任しました。

<つながりが生み出すキラキラ>
協力隊として大きな取組はできなかったけれど、地域の生活文化をみんなで楽しむ会が作れたり、地区で途絶えていた盆踊りを復活することができたり、多くを学ぶ機会だったなぁと感じています。担当させていただいた地区は、自分にとって松之山暮らしの中でふるさとみたいな場所になりましたね。協力隊2年目に、布川カフェっていう集まりの場を作りました。隣近所の仲間でしかお茶飲みする文化がなかった地域に、いつでも誰でもここに来てお茶飲んでいい拠り所ができたんです。同じ地域に住んでても、絶対出会わない人たちがつながって、「あっ、つながるってこんなにキラキラするんだな」って。その経験はいつも根っこにあって、またいつかやりたいなって思ってました。

協力隊をやめて、保育園の給食に入って、3人目が生まれて。そのあと、自治組織の事務局を4年。そこでも生活文化体験を年に2つくらい企画させてもらいました。

<さんビズとの出会い>
さんビズを知ったのは、二期生の阿部美記子さんとの出会いですね。子育てママの声を聞く集まりを市議さんが主催していて、初対面はそこでお互い子連れ。布川カフェみたいな居場所づくりへの想いが高くなってきたときに、美記子さんの活動をSNSで見ていてすごく気になったんです。同じママでこんなに活動を生み出してるのってどういうエネルギーなんだろう、これは肌で感じないと、と思ったんですよね。美記子さんが子育てママの交流の場「むすび」を始めた頃かな。イベントの中でさんビズからエネルギーをもらってるって話を聞いて、ほうほう、と。結果的に仕事として受講することになったけれど、そうでなくても個人的に受講したと思うな。

<みんなが自分らしくいられるまつのやま基地>
さんビズを受けたタイミングは、十日町市の地域支援員の仕事が始まったばかり、2018年の8月からですね。全部が追い風って言うか。支援員をやるときに、協力隊とか自治組織の事務局じゃできないことをやりたいし、だけど地域点検したからってまちづくりが動き出すわけじゃなくて、新しいまちづくりを思い描いていたけど実現できないもどかしさがたくさんで、その中でさんビズを受けられたってのは大きかったなぁと思う。
「まつのやま基地」としてスタートしたこの家も、支援員を始めた年の春に話を持ちかけられて。わたし4人の子育て真っ最中ですよ、家をもう一軒管理するとか、なくないですか?って。でも、布川カフェみたいな場所、みんなが集まってつながって、やりたいことが生まれる場所を作りたいんだなっていうのは、さんビズで形にできた。この場所を引き受けさせてもらう覚悟が試されてるのかなって。

組織の中の事業として始めたかったのだけど、自分の話し合いのスキルのなさからうまく話を展開できなくて。でも今始めたい、じゃあ誰と始めよう、地域づくりの大変さ、楽しさを知っている、そんな協力隊の仲間がいいなって思い立って、声をかけてみたら、みんな「よく分かんないけど、まぁいいよ」って始めてみることになったのが「まつのやま基地」なんです。つながる場所として希望を見てくれたのかな。家庭じゃない、仕事じゃない、個人として地域でいれる場所。こういう場所のために関わってくれたんだな、みたいなのを感じました。

<お金の話から始まらないビジネス講座>
さんビズの何がすごいって、講座の内容もすごいんだけど、その人らしいやりたい事の引き出し力と寄り添い力。そして、いい意味で諦めの悪い榎本さんの伴走力ですよね。これだけ1期生からずっとつながり続けられる講座、ないでしょ。

自分の中でさんビズって、自分らしくやりたいことを、経済活動を使って回すんだなっていうこと。自分らしさとかほんとにやりたいことは何?って、しつこく引きずり出されたお陰で、今そこに落ちてて。起業するにはこういう経済観念が必要です、そして卒業しましたっていうところだけだったら、今に辿り着けてないので。やっぱりお金の方で頭がいっぱいになっちゃうんだと思うんですよ。でも榎本さんが、「えっ、それ佐藤さんらしいの?」ってずっとえぐり続けてくれるお陰で、「あ、そうそう。わたしがやりたいことはこっち、こっち!」って。
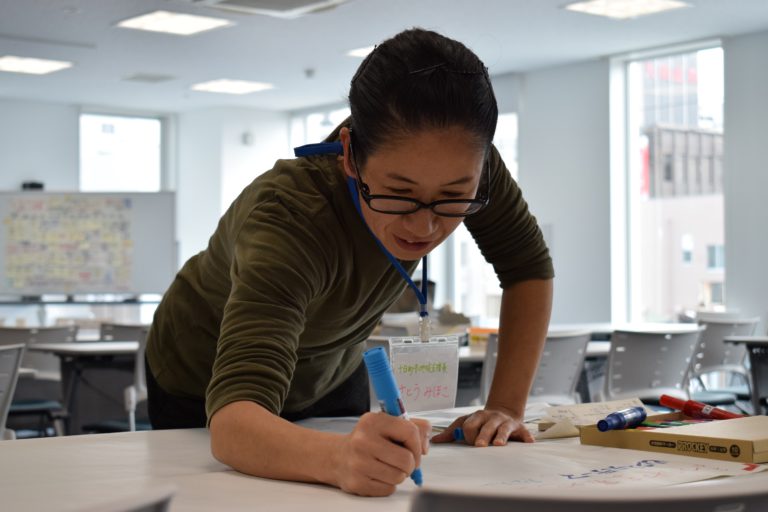
<対話を生み出すコミュニティスペース>
わたしは地域自治の本質とか分かんないけど、松之山の暮らしを未来に残す仕組みを知りたい、ともに生きる地域の人や松之山を好きになってくれる人たちと松之山の今を楽しみたい、そんな想いが「まつのやま基地」にはあります。地域にずっとあるこの生活・文化に、外に出た人間が技とか知識とか知恵とかを、地域に持って帰って来て融合させて、また新しく文化が生まれて発展していくってことを大事にしたい、「まつのやま基地」というコミュニティスペースで地域の人たちが活気づくんだったらぜひ関わりたいって言ってくれる人もいて、あぁ、松之山暮らしへの想いの根っこが共感できる人と出会える場でもあるんだなとも感じています。

支援員の仕事をしながら感じるのは、隣にコンビニがないことがほんとに悩みなのか、って。娯楽を満たすためのスタンダードと、命を守るためのスタンダードの違いにすら気づけない今の人間力とか。たまたま持ち込み企画でしてもらった石けん講座の情報コーナーを基地に作ったら、基地に来た意外な人たちが「そういえばさ、石けんさ。香害さ」みたいな話をしたり。ここには可能性があるんだなって、やりながら気が付いてきたかな。
<松之山で生きて、死ぬということ>
この10年で、本当に自分っていう人間がだいぶ変身を遂げたと思う。除雪重機もトンネルもなかった時代、この雪深いところで半年雪に埋もれながら、それでも笑って生きてきた、生き抜いてきてくれた人たちがいることへの感謝だけは絶対忘れちゃいけないなぁと思って。
自分の死生観にもつながることをこの10年間見せてきてもらったかな。死ぬときにちゃんと自分らしい人生だったっていう身内を、都会生活で見たことがないの。それが松之山では、故人をちゃんと偲び語ってシェアする時間がみんなの中にあった。そういう暮らしをしたくってここに来たんだろうなぁ。

松之山で暮らし続けたいから、暮らし続けるために自分に何ができるだろう、何が一番役に立てるだろうなって。最近は、どんな講座に行っても、最後は自分で考えなさいよ、自分で決めなさいよって言う講師の人ばっかりに出会います。何を学んでも自分らしい生き方に繋げなくちゃ、そんなことを今さら学んでいる感じです。いいこともあれば悪いこともあって、苦しいならその苦しいことも必然で起きてるんだから、きっとこの階段昇って行く先に問題も嬉しいこともどっちもあるから、物事をそんな風にとらえられるようになった今はずいぶん生きやすくなったかも。そんな前のめり思考に追い風をくれているのがさんビズだなぁ、と感じますね。

※この記事は、「聞き書き」の手法によって作成しました。


